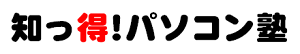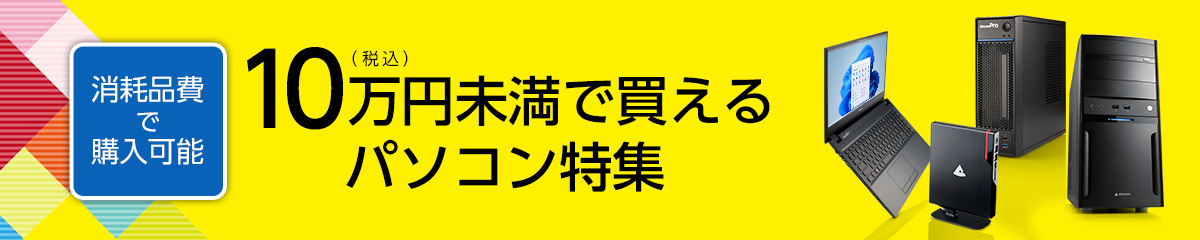事業で使うパソコン、その購入費用はどのように会計処理していますか? 「高い買い物だから、固定資産かな?」と思う方も多いかもしれません。
でも、実は一定の条件を満たせば、パソコンの購入費用を「消耗品費」として計上できる場合があります。そして、これには嬉しいメリットがあるんです!
今回は、パソコン購入費を消耗品費にするメリットと、そのための条件、注意点について分かりやすく解説します。
パソコンは「固定資産」? それとも「消耗品」?
まず、税務上の基本的な考え方から見ていきましょう。
事業のために購入した資産は、その使用可能期間によって「固定資産」または「消耗品」に区分されます。
-
固定資産: 使用可能期間が1年以上で、比較的金額が大きいもの。建物、機械、車両などが該当します。パソコンも通常はこちらに該当することが多いです。固定資産は、購入費用を一度に全額経費にするのではなく、「減価償却」という方法で、決められた年数(耐用年数)にわたって分割して経費にしていきます。
-
消耗品: 使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が少額なもの。文房具やコピー用紙などが該当します。消耗品は、購入した事業年度にその全額を一度に経費として計上できます。
では、パソコンはどちらになるのでしょうか?
パソコンを「消耗品費」にできる条件とは?
税務上、パソコンを消耗品費として扱うためには、主に以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
使用可能期間が1年未満であること
-
取得価額が10万円未満であること
通常、パソコンの使用可能期間は1年以上と考えられますので、多くの場合、「取得価額が10万円未満」であることが消耗品費として計上できるかどうかのポイントになります。
つまり、本体価格が10万円未満のパソコンであれば、購入した年度に全額を「消耗品費」として経費にできる可能性が高いということです。
【知っておきたい特例】中小企業者等の少額減価償却資産の特例
青色申告をしている中小企業者等であれば、さらに有利な特例があります。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用することで、取得価額が30万円未満のパソコンについても、年間合計300万円を上限として、購入した事業年度に全額を一度に経費(この特例では「一括損金算入」と呼ばれます)に算入できます。
この特例を使えば、10万円以上30万円未満のパソコンでも、購入年度に全額経費にできるため、非常に節税効果が高いです。
パソコン購入費を「消耗品費」にするメリット
条件を満たしてパソコンを消耗品費として計上することには、主に3つのメリットがあります。
-
購入した年度に全額経費にできる
これが最大のメリットです。固定資産として減価償却する場合、数年に分けて少しずつ経費になりますが、消耗品費なら購入したその年度に購入金額の100%を経費にできます。
-
節税効果を早く得られる
購入金額全額を一度に経費にできるということは、その年度の所得を大きく減らせるということです。所得が減れば、それにかかる所得税や法人税、住民税などの税金も減ります。減価償却よりも早く、大きな節税効果を実感できます。
-
会計処理が比較的簡単
減価償却計算は、耐用年数や償却方法など、少し複雑な計算が必要です。一方、消耗品費として一括で経費にする場合は、単純に購入金額を計上するだけなので、会計処理の手間が省け、シンプルになります。
注意点
-
上記の条件(10万円未満、または特例利用で30万円未満)を満たさない高額なパソコンは、原則として固定資産として減価償却が必要です。
-
中小企業者等の少額減価償却資産の特例を利用するには、資本金の額などの要件を満たす必要があります。また、適用を受けるためには確定申告書に所定の事項を記載する必要があります。
-
「消耗品費」として処理できるのは、あくまで事業のために使用するパソコンに限られます。プライベートで使用する分は経費にできません。
まとめ
事業用パソコンの購入は、金額によっては消耗品費として一括で経費にできる場合があります。特に取得価額が10万円未満、または中小企業者等であれば30万円未満のパソコンは、消耗品費(または一括損金算入)として処理することで、早期の節税効果や会計処理の簡便さといったメリットが得られます。
ご自身の状況や購入するパソコンの価格に合わせて、最も有利な方法を選択しましょう。判断に迷う場合は、税理士などの専門家や最寄りの税務署に相談することをお勧めします。
賢く経費を計上して、事業の負担を軽減しましょう!